「お金の勉強って、何から始めればいいの?」そんな悩みにズバッと答えてくれるのが、両@リベ大学長の『お金の大学』です。難しい知識がなくても、「貯める・稼ぐ・増やす・守る・使う」の5つの力を身につけるだけで、お金の不安がグッと減っていくのを実感できます。
この記事では、『お金の大学』を読んで感じた初心者にとっての価値や、すぐに行動に移せるポイントをレビュー形式で紹介します。
- 『お金の大学』が支持されている理由
- 5つの力が日常にどう役立つかのヒント
- 初心者が最初に実践すべき行動
- 本を読むだけで終わらせない使い方
目次
- 第1章:『お金の大学』とはどんな本か?
- 第2章:5つの力で学べること
- 第3章:初心者にも最適な理由
- 第4章:読んで実践したリアルな感想
- 第5章:『お金の大学』を活かす読み方
- まとめ:お金の不安を減らす第一歩に
第1章:『お金の大学』とはどんな本か?
著者と出版背景
『お金の大学』は、YouTube「リベ大」で知られる両@リベ大学長が執筆したマネー実用書です。彼はFIRE(経済的自立と早期リタイア)を達成した経験をもとに、初心者でもわかるお金の教養を広める活動を行っており、その集大成としてこの本が出版されました。2020年に発売されて以降、100万部以上を売り上げ、現在もなおビジネス書ランキングの常連です。
本書の内容は「5つの力」(貯める・稼ぐ・増やす・守る・使う)をベースに構成され、全259ページ・フルカラーで構成。イラストや図解も多く、読書が苦手な人でも最後まで読み切れる工夫が随所に施されています。YouTubeと連動して学べる点も、本書ならではの魅力です。
読者層と評価
本書は20〜40代の会社員・主婦・学生など、幅広い層に支持されています。Amazonレビューは5,000件を超え、平均評価★4.5以上を維持。「人生で一番役立った本」という声が多く、「読後すぐに証券口座を開設した」「スマホ代を見直した」といった具体的な行動変化を促しています。まさに「読むだけで人生が変わる」と言っても過言ではない一冊です。
なぜ今話題なのか
2024年の新NISA制度開始や物価高、老後資金への不安が広がる今、「お金の基本から学び直したい」と考える人が増えています。その中で、『お金の大学』は初心者に最適なスタート地点として再注目されています。書店でも平積みが続き、SNSでも「この本で人生が変わった」と話題が絶えません。
次章では、「5つの力」がどのような知識と行動を導いてくれるのかを一つずつ深掘りし、あなたの資産形成にどう役立つかを具体的に見ていきます。
第2章:5つの力で学べること
貯める力と生活防衛
本書で最初に紹介される「貯める力」は、収入をいかに効率よく残すかに焦点を当てています。とくに家計の中でもインパクトの大きい固定費の見直し(スマホ代・保険・家賃など)に重点を置き、月に数万円の改善も可能だと解説されています。「まずは支出のムダを把握する」ことで、自分のお金の流れに責任を持つ意識が芽生えます。最初のアクションとして最適です。
稼ぐ・増やすの実践方法
「稼ぐ力」では、時間単価や副業、転職による年収アップの考え方を紹介。「今の仕事をただ続けるだけでは危うい」という問題提起がなされ、個人で収入を作る力の必要性が強調されています。さらに「増やす力」では、投資信託・iDeCo・NISAなどの制度活用が解説されており、初心者でも理解しやすい構成。資産運用の基礎を固める一歩として、多くの人がこの章で証券口座開設へと動き出しています。
守る・使うで人生が整う
「守る力」では、保険の入りすぎや詐欺から自分のお金を守る方法が紹介されます。過剰な生命保険や情報商材など、知識不足からお金を失わないために、基本的な判断力が必要だとわかります。「使う力」では、お金は貯めるだけでなく人生を豊かにするために使うという価値観が提案されます。浪費との違い、自分が幸せになる支出を意識することで、金額以上の満足感が得られるのです。
| 力の名称 | 主な内容 | 得られる効果 |
|---|---|---|
| 貯める | 固定費の最適化 | 無理せず支出削減 |
| 稼ぐ | 副業・転職戦略 | 収入アップ・自由度向上 |
| 増やす | 資産運用・投資信託 | 将来の安心を作る |
また、本書では「5つの力」を同時に伸ばすのではなく、段階的に身につけることが大切だと説いています。一気にすべてを実践しようとするのではなく、まずは「貯める力」→「稼ぐ力」→「増やす力」という順序を意識することで、無理なく生活に取り入れられる構成になっています。
この章では、5つの力の全体像と学びのポイントを紹介しました。次章では、『お金の大学』がなぜ初心者に最適な一冊と言われているのか、その理由を具体的に掘り下げていきます。
第3章:初心者にも最適な理由
難しい言葉を使わない
『お金の大学』の大きな特徴は、専門用語をできる限り排除し、中学生でも理解できるレベルで書かれている点です。例えば「リスク」や「インデックス投資」といった用語も、難しい言い回しではなく、日常生活に置き換えて説明されています。初心者がつまずきやすい壁を丁寧に取り除いているため、読み進めるごとに自然と知識が身についていく感覚があります。
具体例と図解のわかりやすさ
文章だけでは伝わりにくい部分も、イラストや図解を活用することで視覚的に理解をサポートしています。たとえば「家計の見直し」の図では、スマホ代・保険・家賃などの項目ごとに改善効果を視覚化し、どこから手をつけるべきかが一目瞭然になります。
読後に行動できる設計
『お金の大学』は、読むだけで終わらせないための工夫もされています。章ごとに「やることリスト」が明記されており、読後すぐに実生活に活かせるよう設計されています。読者が「次に何をすればいいか」までわかるという点は、他のマネー本との大きな違いです。
| ステップ | やること | 難易度 |
|---|---|---|
| STEP1 | 支出の記録と見直し | 易 |
| STEP2 | 証券口座の開設 | 中 |
| STEP3 | 投資信託の購入 | 中 |
また、全体を通してユーモアを交えた語り口になっているため、「お金の話は難しそう」と敬遠していた読者にもスッと入ってくる設計になっています。堅苦しい表現や専門的な文体は避けられており、読者と同じ目線で書かれていることが、最後まで読み切れる大きな理由のひとつです。
「読んで終わりではなく、読み終わったあとに何かが変わる本」。それが本書の最大の強みです。学んだ知識を行動に落とし込める仕掛けがあるからこそ、多くの人が実際に生活を変えるきっかけを掴んでいます。
この章では、「初心者でも挫折せずに読み進められる理由」について解説しました。次章では、実際に読んで行動した人たちのリアルな感想や体験談を紹介していきます。
第4章:読んで実践したリアルな感想
生活費の見直し
本書を読んで最初に取り組んだのが「固定費の見直し」でした。スマホ代を格安SIMに変更し、保険も見直して不要な特約を解約。結果として月々1万5千円以上の支出が減り、手取りが増えたような感覚を得られました。これだけで本の元は十分に取れたと思えた瞬間です。
副業への一歩
「稼ぐ力」の章を読んで、副業への意識が変わりました。すぐにできそうなスキルを棚卸しし、クラウドソーシングでプロフィールを作成。初案件はたった500円の文字起こしでしたが、「自分の力で稼いだ!」という達成感は大きかったです。
投資信託で資産形成開始
本の後半で紹介されていた「増やす力」の実践として、SBI証券でつみたてNISAをスタートしました。投資は怖いという先入観があったものの、「長期・分散・積立」という基本を知ったことで、不安が徐々に解消されていきました。
| 実践内容 | 具体的な行動 | 効果・気づき |
|---|---|---|
| 生活費の見直し | スマホ・保険見直し | 月1.5万円の固定費削減 |
| 副業開始 | クラウドソーシング登録 | 稼ぐ自信がついた |
| 投資信託 | つみたてNISA開始 | 将来の資産形成に希望 |
最初の実践はどれも小さな行動でしたが、実際にやってみると「やればできる」感覚が積み上がっていきました。節約も副業も投資も、最初の一歩を踏み出せば驚くほど心理的なハードルは下がります。本書はそれを自然に導いてくれる存在でした。
何より印象的だったのは、すべての章が「行動すること」を前提に書かれていた点です。ただ読んで満足するのではなく、具体的なアクションにまで落とし込める構成。読むだけで終わらないマネー本という評価は、まさにこの設計思想に支えられていると感じました。
この章では、本書を読んで実際に行動に移したリアルな体験をまとめました。次章では、そんな実践を継続していくために、本書をどう読み進めていくべきかをご紹介します。
第5章:『お金の大学』を活かす読み方
全体を一気に読まなくてもOK
本書は「貯める・稼ぐ・増やす・守る・使う」という5つの力を紹介していますが、最初から順番に読む必要はありません。自分の課題や興味があるところから読み始めても、内容はきちんとつながるように構成されています。「今の自分に必要な知識だけを先取りできる」のが、この本の柔軟さです。
自分の課題から読む
たとえば「まずは固定費を見直したい」という人は「貯める力」から、「副業を始めたい」という人は「稼ぐ力」から、「NISAやiDeCoを知りたい」という人は「増やす力」の章から読むと良いでしょう。一人ひとりの状況に応じたアプローチが可能です。
実生活に落とし込む工夫
本書を活かす最大のコツは「読んだらすぐに1つでも実行してみること」。内容をノートに書き出す、スマホのメモにチェックリストを作るなど、行動と結びつけて初めて知識が血肉になるのです。
| 読み方 | おすすめの活用法 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 課題ベース読み | 自分に合った章から読む | 効率よく情報を吸収できる |
| メモ読書 | 気づきをスマホにメモ | 実行率が高まる |
| 家族と共有 | パートナーと感想を話す | 金銭感覚が揃う |
「お金の大学」は、単に知識を得るためだけの本ではありません。繰り返し読み返すことで、ライフステージや収入状況に応じた再発見があります。たとえば、学生のうちは「貯める力」、社会人になったら「稼ぐ力」、家族を持ったら「守る力」など、段階に応じた読み直しが効果的です。
実際に私も半年後に再読した際、「あのときはスルーしていた副業の章が、今は一番響く」と感じた経験があります。ライフステージが変わるたびに学びが深まる、そんな一冊として手元に置いておく価値は大きいと実感しました。
この章では、『お金の大学』をどう読めば「行動につながる読み方」になるかを紹介しました。最後はこの本を読んで得られる最大のメリット=お金の不安を減らす効果についてまとめていきます。
まとめ:お金の不安を減らす第一歩に
『お金の大学』は、単なるマネー本ではなく、人生の選択肢を広げてくれる「実践型の教科書」です。貯める・稼ぐ・増やす・守る・使うという5つの力を通じて、お金に対する前向きな向き合い方を学ぶことができました。
読み終えて実感するのは、「知らなかった」ことがどれだけ損につながっていたか、という現実。知ることで人生の舵を自分で握れるようになる。この感覚を一人でも多くの人に味わってほしいと思います。
もちろん、本を読んだだけで人生は変わりません。しかし、「行動に移すヒント」が詰まっているからこそ、一歩踏み出す後押しをしてくれるはずです。小さな節約でも、副業でも、投資でもいい。今の自分にできることから始めてみましょう。
本書を通じて最も感じたのは、「お金の不安は知識で薄まる」ということです。収入が増えなくても、支出をコントロールし、将来に備える仕組みを持つだけで心に余裕が生まれます。心のゆとり=選択肢の多さだと気づかされました。
「お金の大学」は、すぐに読み終わるのに、一生使える知識が詰まっています。そして何より、読者に「やってみよう」と思わせてくれる工夫が満載です。最初の一歩を踏み出す勇気が欲しい人に、ぜひ手に取ってもらいたい1冊です。
最後に、あなたは今日から何を始めますか?この記事が、そのヒントやきっかけとなれば嬉しいです。
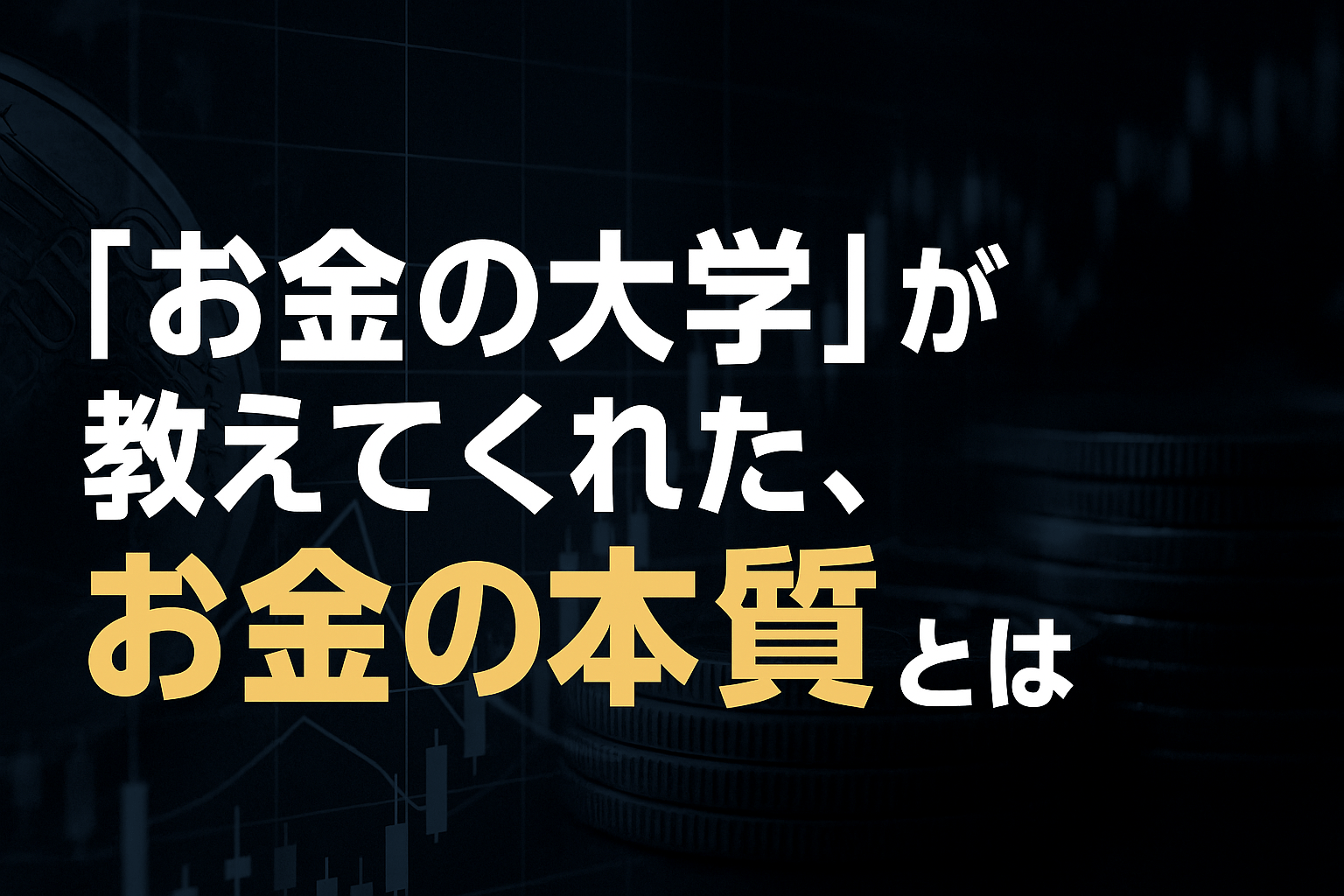

コメント