この記事でわかること
- 高配当ETFの落とし穴と投資前に知るべきリスクの本質
- 表面利回りに騙されない真のリターン評価方法
- 他の優良高配当ETFとの決定的な違いと選択基準
- 税制面・為替リスクが投資成果に与える実際のインパクト
- あなたの投資目的に適したETF選択の判断軸
第1章:SPYDがおすすめしない理由の核心

「高配当ETFなら安心でしょ?」そんなふうに考えている投資初心者の方は、ちょっと待ってください。確かにSPYDは年4回の配当で人気を集めていますが、実はその裏には見逃せない大きな問題が隠れているんです。
投資を始めたばかりの方にとって、「高配当」という言葉はとても魅力的に感じるはずです。毎年決まった時期にお金がもらえるなんて、まるで給料みたいで安心感がありますよね。しかし、SPYDには専門家が口を揃えて「おすすめしない」と言うだけの、しっかりとした理由があります。
この章では、SPYDの3つの根本的な問題について、できるだけわかりやすく解説していきます。数字やグラフが苦手な方でも理解できるように、身近な例を使いながらお話ししますので、安心して読み進めてくださいね。
配当の不安定性と減配実績の深刻さ
まず最初に知っておいてほしいのは、SPYDの配当は決して安定していないということです。「高配当ETF」と聞くと、毎回同じような金額がもらえるイメージを持つかもしれませんが、実際はそうではありません。
SPYDが設定されてから現在まで、なんと36回の配当のうち、増配(前回より配当が増えた)が12回なのに対して、減配(前回より配当が減った)が14回もあるんです。これって、普通に考えるとちょっと心配になりませんか?
特に2020年のコロナウイルスの影響を受けた時期には、配当が大幅に減ってしまいました。例えるなら、毎月もらっていたお小遣いが、急に半分になってしまったような状況です。配当収入を生活の一部として計算していた投資家の方々は、きっと大変な思いをされたことでしょう。
💡 なぜSPYDの配当は不安定なの?
SPYDは「今、配当利回りが高い会社」を機械的に選んで投資するETFです。でも、配当利回りが高いということは、その会社の株価が下がっている可能性もあるんです。業績が悪くなって株価が下がり、結果的に配当利回りが高く見えているだけの会社も混じってしまうため、配当が不安定になりやすいんですね。
トータルリターンの市場平均劣後問題
次に、SPYDの最も大きな問題点をお話しします。それは、長期的に見ると、お金が思ったほど増えないということです。
投資をする時に大切なのは「トータルリターン」という考え方です。これは、配当でもらえるお金と、株価が上がることで得られるお金を合計した利益のことを指します。SPYDは確かに配当はもらえますが、株価の成長がとても弱いんです。
具体的な数字で見てみましょう。過去約9年間で、アメリカの株式市場全体(S&P500)は約181%も値上がりしました。つまり、100万円投資していたら281万円になったということです。一方、SPYDはたったの31%程度の上昇にとどまっています。100万円が131万円にしかならなかったんですね。
| 比較項目 | S&P500 | SPYD |
|---|---|---|
| 9年間の成長率 | 約181% | 約31% |
| 100万円の投資結果 | 約281万円 | 約131万円 |
| 差額 | – | 150万円の差 |
この150万円の差は、決して小さくありませんよね。新車が買えるくらいの金額です。配当をもらっても、これだけの差が生まれてしまうということは、長期投資を考えている方にとって大きな問題と言えるでしょう。
構成セクター偏重による景気変動リスク
最後に、SPYDの構成についてお話しします。SPYDは特定の業界に偏りすぎているという問題があります。
SPYDが投資している会社を業界別に見ると、不動産関連が約23%、電気・ガスなどの公益事業が約18%、食品や日用品の会社が約15%、銀行などの金融業が約14%となっています。つまり、全体の70%がこれらの業界に集中しているんです。
なぜこれが問題なのでしょうか?例えば、金利が上がる時期を考えてみてください。金利が上がると、不動産会社や公益事業の会社の株価は下がりやすくなります。なぜなら、お金を借りるコストが高くなったり、高い配当を出している魅力が薄れたりするからです。
実際に、コロナショックの時にはSPYDの価格が市場全体以上に大きく下落しました。まるでドミノ倒しのように、似たような業界の会社が一斉に売られてしまったんです。
一方で、最近成長著しいIT関連の会社への投資は極端に少なくなっています。AppleやMicrosoftのような会社は、SPYDにはほとんど含まれていません。これらの会社は配当よりも成長に投資しているため、SPYDの選択基準に当てはまらないからです。
このように、SPYDは「今高配当な会社だけ」を選ぶという方法のため、どうしても業界が偏ってしまい、景気の変動に弱い構造になってしまっているんです。投資の基本である「分散投資」という観点から見ると、少し心配な構成と言えるでしょう。
ここまで見てきたように、SPYDには配当の不安定さ、成長性の低さ、そして業界の偏りという3つの大きな問題があります。次の章では、他の人気ETFと比較しながら、これらの問題をより詳しく見ていきましょう。
第2章:SPYDと他ETFの決定的な違いとデメリット

「SPYDってそんなに悪いの?他の高配当ETFと比べてどうなの?」と疑問に思っている方も多いでしょう。確かに、一つのETFだけを見ていても、その良し悪しはなかなか判断できませんよね。
実は、アメリカには他にも人気の高配当ETFがあります。VYM(バンガード・米国高配当株ETF)やHDV(iシェアーズ・コア米国高配当株ETF)といった商品です。これらと比較することで、SPYDの問題点がより明確に見えてきます。
この章では、2024年から始まった新NISA制度も踏まえながら、SPYDと他の高配当ETFの違いを詳しく比較していきます。また、実際に投資する際に知っておくべき税金や為替の問題、そして将来のインフレリスクについても、具体的な数字を使ってわかりやすく説明します。きっと「なるほど、そういうことだったのか」と納得していただけるはずです。
VYM・HDVとのパフォーマンス比較分析
まず、同じ高配当ETFでも、その中身は全然違うということを知ってください。SPYDは配当利回りだけを重視して銘柄を選びますが、VYMやHDVはもう少し慎重なアプローチを取っています。
VYMは約400~500の銘柄に幅広く分散投資をしています。まるで「バランスの取れた弁当」のように、いろいろな業界の会社に少しずつ投資することで、リスクを抑えようとしているんです。一方、HDVは約75の銘柄に厳選投資をしています。これは「質の高い食材だけを選んだ高級弁当」のようなイメージですね。
そして、SPYDはというと、80の銘柄に等金額で投資をしています。「今日一番安い食材だけで作った弁当」と言えるかもしれません。安いのは魅力的ですが、品質や栄養バランスは心配になりますよね。
実際のパフォーマンスを見てみましょう。過去約9年間で、VYMは80%以上の成長を見せました。HDVも45%前後の堅実な成長を続けています。一方、SPYDは31%程度の成長にとどまっています。
配当利回りで見ても、SPYDが4%台後半なのに対して、VYMは約3%、HDVは約3.5%程度です。確かにSPYDの方が高配当ですが、それを考慮してもトータルの投資成果では大きな差がついてしまっています。
これはどういうことでしょうか?配当が高くても、その分株価が下がりやすかったり、将来的な成長が見込めなかったりすると、結局のところ投資家にとってはマイナスになってしまうということなんです。
| ETF名 | 投資方針 | 銘柄数 | 9年間リターン |
|---|---|---|---|
| SPYD | 配当利回り重視 | 80銘柄 | 約31% |
| VYM | 幅広い分散投資 | 400-500銘柄 | 約80% |
| HDV | 質重視・厳選投資 | 75銘柄 | 約45% |
新NISA制度では年間最大360万円まで非課税で投資できるようになり、さらに非課税期間が無制限となりました。つまり、一度投資すればずっと税金を払わずに保有できるんです。せっかくのこの素晴らしい制度を活用するなら、より成長が期待できるETFを選びたいものです。
特に、生涯投資枠が1,800万円という大きな金額になったことで、長期的な資産形成における投資先選びの重要性がより高まっています。SPYDのように成長性に課題のあるETFに貴重な投資枠を使うのは、もったいないかもしれませんね。
税制面・為替リスクの実際のインパクト
次に、実際にお金を受け取る時の話をしましょう。アメリカのETFに投資すると、配当をもらう時に必ず税金がかかります。そして、この税金の仕組みが、思っているより複雑なんです。
まず、アメリカで10%の税金が自動的に引かれます。これは、新NISA口座で投資していても避けることができません。つまり、SPYDで年間配当利回りが5%だったとしても、実際には4.5%しかもらえないということです。
新NISA制度の大きなメリットは、日本での20.315%の税金がかからないことです。しかし、アメリカの源泉税10%は避けられないため、完全に非課税というわけではないんです。これは、アメリカのETF投資における避けられないコストと考える必要があります。
さらに、為替の影響も無視できません。例えば、1ドル=150円の時にSPYDを100万円分買ったとします。その後、円高が進んで1ドル=130円になったとしましょう。この場合、ドル建てでは利益が出ていても、円に換算すると損失が出る可能性があります。
具体的に計算してみましょう。1ドル=150円の時に100万円でSPYDを買うと、約6,667ドル分のETFを購入できます。1年後、配当を5%もらったとすると、約333ドルの配当金です。しかし、この時に円が130円になっていたら、333ドルは43,290円にしかなりません。150円だったときなら49,950円だったので、6,660円も少なくなってしまいます。
💡 為替リスクってどれくらい影響するの?
為替は時として大きく変動します。過去5年間を見ても、1ドルは100円から150円の間で動いています。つまり、最大で50%も価値が変わる可能性があるということです。これは配当利回りよりもはるかに大きな影響を与える可能性があります。新NISA制度で無制限に保有できるからこそ、こうした為替変動リスクも長期的な視点で考える必要があります。
このように、表面的な配当利回りだけを見ていると、実際に手元に残るお金は思っているより少なくなってしまう可能性があります。特に、新NISA制度を使って長期投資を考えている方は、こうした税金や為替の影響もしっかりと考慮して投資判断をする必要があります。
インフレ耐性の弱さと購買力維持の課題
最後に、将来のお金の価値についてお話しします。これは多くの投資初心者の方が見落としがちな、とても重要なポイントです。
インフレとは、物価が上がることです。例えば、今100円で買えるパンが、10年後には150円になっているかもしれません。もし配当収入が100円のままだったら、実質的には購買力が下がってしまいますよね。
SPYDのような高配当ETFに投資する人の多くは「将来、配当収入で生活したい」と考えています。しかし、SPYDの配当は決して安定して増えているわけではありません。むしろ、減配も多く経験しているのが実情です。
一方で、アメリカでは近年インフレ率が上昇しています。2021年から2022年にかけては、年間7%を超えるインフレが起こりました。もしSPYDの配当が年5%しか増えなかったら、実質的には損をしていることになってしまいます。
実際の生活で考えてみましょう。現在、月20万円の配当収入があったとします。10年後、物価が50%上がっていたら、同じ生活をするためには月30万円が必要になります。しかし、SPYDの配当がそこまで増える保証はありません。
成長株中心のETFなら、企業の業績向上とともに株価も配当も増える可能性があります。しかし、SPYDは既に成熟した企業が中心のため、大幅な成長は期待しにくいのが現実です。
これが、多くの専門家がSPYDよりもS&P500連動のETFや、成長性のある銘柄を含むVYMなどをおすすめする理由の一つです。配当収入は魅力的ですが、長期的な資産形成を考えるなら、インフレに負けない成長力も重要なんですね。
新NISA制度では非課税期間が無制限になったことで、本当の意味での「一生もの」の投資が可能になりました。この素晴らしい制度を最大限活用するなら、目先の配当利回りよりも、インフレに負けない成長力を持つ投資先を選ぶことが、将来の豊かな生活につながるのではないでしょうか。
また、生涯投資枠1,800万円という大きな枠があるからこそ、慎重な投資先選びが重要になります。一度SPYDのような成長性の低いETFに投資枠を使ってしまうと、後で売却しない限りその枠は戻ってきません。長期的な視点で、本当に価値のある投資先を選びたいものですね。
ここまで見てきたように、SPYDは他の高配当ETFと比較しても劣る部分が多く、税金や為替、インフレといったリスクも抱えています。では、どのような投資戦略を取るべきでしょうか?次の章で、SPYDに代わる賢い投資法について詳しく解説していきます。
第3章:SPYDに代わる賢い高配当投資戦略
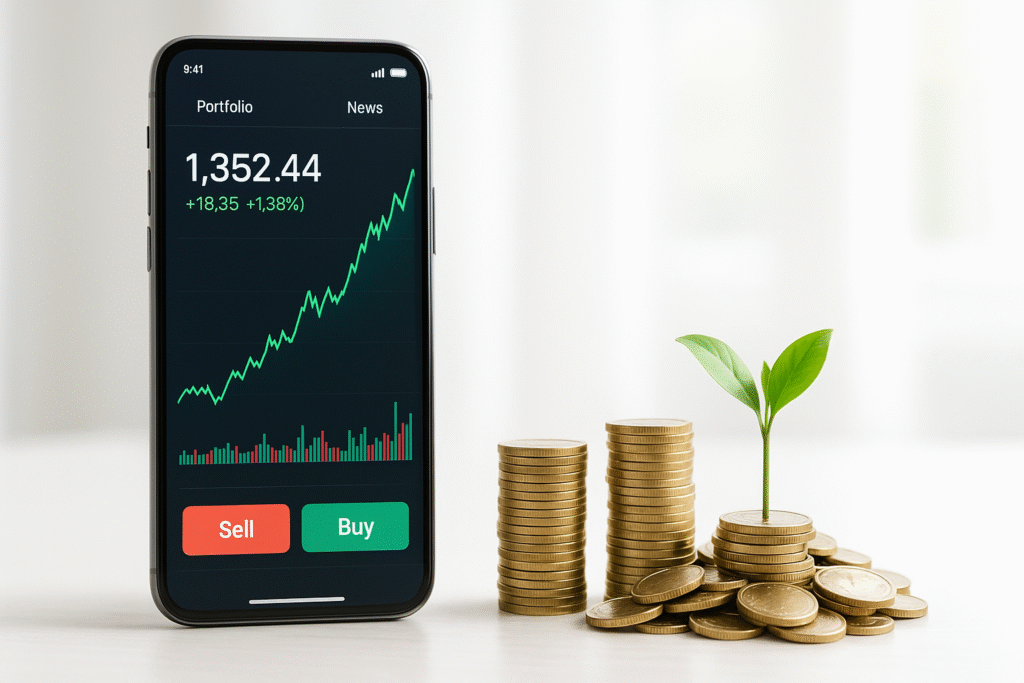
「SPYDがおすすめできないのはわかったけど、じゃあどうすればいいの?」と思っている方、お待たせしました。ここからは前向きな話をしていきましょう。
実は、SPYDよりもずっと優秀な投資先がたくさんあります。しかも、新NISA制度のおかげで、これまで以上に有利な条件で投資を始めることができるんです。無制限の非課税期間と1,800万円の生涯投資枠を活用すれば、本当に豊かな将来を築くことができるかもしれません。
この章では、SPYDの代わりになる具体的な投資戦略をご紹介します。あなたのリスク許容度や投資目標に合わせて選べるように、いくつかのパターンを用意しました。きっと「これなら自分にもできそう」と思える方法が見つかるはずです。
優良代替ETFの選択基準と具体的銘柄
まず、SPYDに代わる優良なETFを選ぶ時のポイントをお話しします。単に「人気だから」「利回りが高いから」という理由だけで選ぶのではなく、しっかりとした基準を持つことが大切です。
良いETFを選ぶための3つのポイントがあります。1つ目は「分散性」です。特定の業界に偏りすぎず、幅広い企業に投資しているETFの方が安定性が高くなります。2つ目は「成長性」です。配当だけでなく、株価の上昇も期待できるETFを選びましょう。3つ目は「コストの低さ」です。経費率が低いETFを選ぶことで、長期的なリターンを最大化できます。
これらの基準に照らして、おすすめできるETFをいくつかご紹介します。まず、VYM(バンガード・米国高配当株ETF)です。約400銘柄に分散投資しており、SPYDよりもはるかにバランスが取れています。経費率も0.06%と非常に低く、長期投資に適しています。
次に、HDV(iシェアーズ・コア米国高配当株ETF)もおすすめです。財務健全性を重視した銘柄選択により、減配リスクを抑えています。約75銘柄と少数精鋭ですが、質の高い企業に厳選投資しています。
さらに、高配当にこだわらないなら、VOO(バンガード・S&P500ETF)やVTI(バンガード・トータル・ストック・マーケットETF)も素晴らしい選択肢です。これらは配当利回りこそ2%前後と低めですが、長期的な成長力では圧倒的に優れています。
💡 新NISA制度でのETF投資のコツ
新NISA制度では、つみたて投資枠(年間120万円)と成長投資枠(年間240万円)の2つがあります。つみたて投資枠では投資信託の積立に限定されますが、成長投資枠では個別のETF購入も可能です。成長投資枠を活用して、優良なアメリカETFに投資するのがおすすめです。ただし、アメリカETFは最低投資金額が1万円程度からと、少し敷居が高い場合があります。
実際の投資例を考えてみましょう。月に10万円の投資予算がある場合、つみたて投資枠で8万円をS&P500連動の投資信託に積み立て、成長投資枠で2万円をVYMやHDVなどの高配当ETFに投資するという方法があります。これなら、成長性と配当収入の両方を狙えます。
また、投資初心者の方には、まずは投資信託から始めることをおすすめします。eMAXIS Slim米国株式(S&P500)やSBI・V・S&P500インデックス・ファンドなど、コストが低く優秀な投資信託がたくさんあります。慣れてきたら、ETFにも挑戦してみるという段階的なアプローチが良いでしょう。
リスク許容度別のポートフォリオ構築法
投資で大切なのは、自分のリスク許容度に合った投資をすることです。「みんなが言うから」「雑誌に書いてあったから」という理由ではなく、あなた自身の状況に合わせて投資戦略を決めましょう。
リスク許容度は、年齢、収入の安定性、投資経験、性格などによって決まります。ここでは、3つのパターンに分けてポートフォリオの例をご紹介します。
【保守的な投資家向け】40代以上の方や、リスクを抑えたい方におすすめです。S&P500連動の投資信託40%、VYM(バンガード・米国高配当株ETF)30%、HDV(iシェアーズ・コア米国高配当株ETF)20%、現金10%という配分です。配当収入を重視しつつ、リスクも抑えた構成になっています。
【バランス重視の投資家向け】30代〜40代前半の方や、成長と安定のバランスを取りたい方に適しています。S&P500連動の投資信託60%、VYM 25%、HDV 15%という配分です。成長性を重視しながらも、配当収入も確保できます。
【積極的な投資家向け】20代〜30代前半の方や、長期的な成長を最優先したい方向けです。S&P500連動の投資信託70%、全世界株式の投資信託20%、VYM 10%という構成です。配当よりも成長を重視し、時間を味方につけた投資戦略です。
| ETF名 | 特徴 | 経費率 | 配当利回り目安 |
|---|---|---|---|
| VYM | 幅広い分散、安定性重視 | 0.06% | 約3.0% |
| HDV | 財務健全性重視、質の高い銘柄 | 0.08% | 約3.5% |
| VOO | S&P500連動、成長性重視 | 0.03% | 約1.5% |
重要なのは、一度決めたポートフォリオを頻繁に変えないことです。市場が下落したからといって慌てて売却したり、流行に流されて投資先をころころ変えたりするのは、長期投資の大敵です。
また、新NISA制度では売却しても投資枠が翌年に復活します。しかし、頻繁な売買は手数料もかかりますし、税制上のメリットを最大限活用するためにも、長期保有を基本とすることをおすすめします。
長期的な資産成長を重視した投資アプローチ
最後に、本当に豊かな将来を築くための投資の考え方についてお話しします。SPYDのような目先の配当にとらわれるのではなく、長期的な視点で資産を育てていくことが大切です。
長期投資の最大の武器は「複利の力」です。例えば、毎月5万円を年利7%で30年間投資し続けると、投資元本1,800万円に対して、最終的な資産は約6,100万円になる計算です。つまり、4,300万円もの利益が生まれる
まとめ:SPYDおすすめしない理由を踏まえた投資判断
ここまで読んでくださって、本当にありがとうございました。SPYDについて、きっと新しい見方ができるようになったのではないでしょうか。
この記事でお伝えした最も大切なポイントは、「高配当」という魅力的な言葉に惑わされず、本質を見極めることの重要性です。SPYDは確かに高い配当利回りを誇りますが、配当の不安定性、成長性の低さ、セクター偏重リスク、税制面・為替面でのデメリットなど、多くの課題を抱えています。
しかし、これは決してネガティブな話ではありません。むしろ、あなたがより良い投資判断を下すための貴重な気づきです。SPYDの代わりに、VYMやHDV、そしてS&P500連動の投資信託など、より優秀な選択肢があることがわかりました。
特に、2024年から始まった新NISA制度は、私たちにとって本当に素晴らしいチャンスです。非課税期間が無制限で、生涯投資枠は1,800万円。この制度を最大限活用すれば、将来の経済的自由に大きく近づくことができるでしょう。
「でも、投資って難しそう」「失敗したらどうしよう」そんな不安を感じているかもしれませんね。でも大丈夫です。まずは小さな一歩から始めてみてください。月1万円でも、3万円でも、あなたができる範囲で構いません。
投資に完璧なタイミングなんてありません。大切なのは、始めることです。そして続けることです。時間を味方につけて、複利の力を活用すれば、きっと想像以上の成果を手にできるはずです。
最後に、一つお願いがあります。この記事で得た知識を、ぜひ周りの大切な人たちにも教えてあげてください。正しい投資の知識が広まることで、より多くの人が豊かな未来を築けるようになります。
あなたの投資人生が、豊かで実り多いものになることを心から願っています。新NISA制度という強力な武器を手に、賢い投資戦略で素晴らしい未来を切り開いていきませんか?

コメント