「楽天VTIはもうオワコン」「SBIの方がコストが安い」SNSでこんな声を見かけて、不安になっていませんか?実は、こうした評価は短期的な視点やコスト面の一部だけを見た誤解に過ぎません。最新データによると、楽天VTIは3年で年率29%超、5年で年率22%超という優秀な実績を維持しており、2026年も米国株式市場の成長が期待されています。本記事では、楽天VTIが「オワコンではない」根拠を、具体的な数字と最新の市場動向をもとに徹底解説します。
この記事でわかること
- 楽天VTIの実際のパフォーマンスと最新の運用実績データ
- 「オワコン」と言われる理由の真相とよくある誤解の正体
- コスト差よりも重要な長期投資で成功するための判断基準
- 新NISA活用と2026年以降の米国株式市場の成長見通し
- 楽天VTI継続または乗り換えを判断する具体的なチェックリスト
第1章:楽天VTIがオワコンと言われる3つの理由を検証

「楽天VTIはもうオワコン」という声を、SNSやブログで見かけたことはありませんか?実は、この評価には3つの具体的な理由があります。でも、それらは本当に「終わっている」証拠なのでしょうか?この章では、オワコンと言われる理由を一つひとつ検証し、誤解と真実を切り分けていきます。
📊 コスト競争激化の実態と信託報酬の比較データ
楽天VTIが「オワコン」と言われる最大の理由は、コストの高さです。近年、低コストを売りにする競合ファンドが次々と登場し、楽天VTIの信託報酬は相対的に高く見えるようになりました。特に、SBI証券が提供する「SBI・V・全米株式インデックス・ファンド」は、楽天VTIよりも大幅に低い信託報酬を実現しています。
では、実際にどれくらいの差があるのでしょうか?最新データを表で比較してみましょう。
| ファンド名 | 信託報酬(年率) | 実質コスト(年率) |
|---|---|---|
| 楽天・全米株式(楽天VTI) | 0.132% | 0.162~0.183% |
| SBI・V・全米株式 | 0.0638% | 0.0938% |
| 本家VTI(ETF) | 0.03% | 0.03% |
この表を見ると、楽天VTIの実質コストは約0.18%で、SBI・V・全米株式の0.09%と比べて約2倍の差があることがわかります。この差は一見小さく見えますが、長期投資では大きな影響を与える可能性があります。
例えば、毎月3万円を30年間積み立てた場合を考えてみましょう。年率5%のリターンを前提とすると、コスト差0.09%でも最終的な資産額には数十万円の差が生まれる計算になります。これが「オワコン」と言われる理由の一つです。
しかし、ここで重要なポイントがあります。コストの差はたしかに存在しますが、それよりも「投資を継続できるかどうか」の方が最終的な成果に大きく影響するのです。コストばかりを気にして、頻繁にファンドを乗り換えたり、市場が下落したときに売却してしまうと、コスト削減以上の損失を被る可能性があります。
💱 為替リスクが基準価額に与える影響とは
楽天VTIがオワコンと言われる2つ目の理由は、為替リスクです。楽天VTIは米国株式に投資するファンドなので、日本円で購入しても実際には米ドル建ての資産を保有していることになります。そのため、円高・円安の影響を大きく受けるのです。
具体的に説明しましょう。2022年のように急激な円安が進むと、米国株式そのものの価格が変わらなくても、円換算での基準価額は大きく上昇します。実際、2022年には1ドル=150円近くまで円安が進み、楽天VTIの基準価額も大きく上昇しました。この時期に投資していた人は、為替の恩恵を受けた形になります。
しかし、逆に円高局面ではどうでしょうか?例えば、1ドル=150円から1ドル=130円に戻った場合、米国株式が上昇していても円換算での基準価額は伸び悩むか、場合によっては下落することもあります。これが「為替リスク」と呼ばれるものです。
💡 為替の影響を具体例で理解しよう
購入時:1ドル=110円、基準価額10,000円
米国株+10%上昇 → ドル建ては11,000円相当
でも、為替が1ドル=100円(円高)になると…
円換算では10,000円に戻ってしまう!
このように、株価が上がっても為替で相殺されることがあります。
ただし、為替リスクは長期投資では平均化されるという特徴があります。毎月一定額を積み立てる「ドルコスト平均法」を使えば、円高のときには多く買い、円安のときには少なく買うことで、為替変動の影響を自然に分散できます。
実際、過去20年間のデータを見ると、為替は上下を繰り返しながらも、米国株式市場の成長がそれを上回るペースで進んでいます。短期的な為替変動に一喜一憂せず、10年、20年という長期視点で見ることが大切なのです。
📉 短期的な下落がもたらす心理的バイアスの罠
楽天VTIがオワコンと言われる3つ目の理由は、短期的な価格下落による心理的な影響です。投資を始めたばかりの人が、市場の調整局面でマイナスになった口座を見ると、「もう終わった」「失敗した」と感じてしまうのは自然なことです。
2022年や2023年初頭のように、米国株式市場が大きく調整した時期がありました。このとき、SNSやネット掲示板には「楽天VTIが下がった」「損切りすべきか」といった不安の声があふれました。こうした声が拡散されることで、「楽天VTIはもうダメだ」という印象が広まってしまったのです。
しかし、これは心理的バイアスによる誤解です。投資の世界では、短期的な下落は避けられません。過去のデータを見ても、米国株式市場は何度も調整を経験しながらも、長期的には右肩上がりで成長してきました。
例えば、2008年のリーマンショックでは米国株式市場は一時50%以上下落しましたが、その後10年で元の水準を大きく超えて回復しました。2020年のコロナショックでも、一時的に30%以上下落しましたが、わずか数か月で回復し、その後も成長を続けています。
重要なのは、短期的な価格変動に惑わされず、長期的な視点を持つことです。積立投資を継続していれば、下落局面は「割安で買えるチャンス」になります。実際、定額積立を続けている人ほど、下落後の回復局面で大きなリターンを得ています。
また、SNSやブログの情報は、感情的な内容ほど拡散されやすい傾向があります。「儲かった」「損した」という極端な体験談は目につきやすいですが、実際には地道に積立を続けて成果を出している人の方が圧倒的に多いのです。ただ、そうした成功例は地味で話題にならないだけです。
結論として、楽天VTIが「オワコン」と言われる理由は、①コスト競争の激化、②為替リスク、③短期的な下落による心理的影響の3つです。しかし、これらはすべて短期的な視点や一面的な評価に基づいています。次章では、これらの「オワコン説」を覆す、楽天VTIの実力を数字で証明していきます。
第2章:楽天VTIの実力を数字で証明|最新パフォーマンス分析

前章では「オワコン」と言われる理由を見てきましたが、では実際の運用成績はどうなのでしょうか?この章では、具体的な数字とデータをもとに、楽天VTIの真の実力を検証していきます。結論から言うと、楽天VTIのパフォーマンスは依然として世界トップクラスの水準を維持しています。
📈 3年・5年リターンが示す圧倒的な運用実績
投資信託の実力を測る最も確実な方法は、過去の運用実績を見ることです。楽天VTIの最新データ(2026年1月時点)を確認すると、驚くべき数字が明らかになります。
まず、3年間の年平均リターンは29.06~29.14%です。これは、100万円を投資していれば3年後には約215万円になる計算です。さらに、5年間の年平均リターンは22.10~22.81%となっており、100万円が5年後には約270万円に成長する水準です。
🎯 実際の積立シミュレーション
毎月3万円を5年間積立した場合(年率22%想定)
・投資元本:180万円
・運用資産:約295万円
・利益:約115万円(+64%)
新NISA活用なら、この利益が全額非課税になります!
これらの数字は、日本国内の投資信託と比較しても圧倒的に優秀です。国内株式ファンドの平均リターンが5~10%程度であることを考えると、楽天VTIの20%超えという成績がいかに素晴らしいかがわかります。
また、2026年1月時点での基準価額は約40,000円台で推移しており、設定来(2017年9月から)の累計リターンは約300%以上に達しています。つまり、設定当初に100万円投資していれば、約8年半で400万円近くになっている計算です。
もちろん、これは過去の実績であり、将来も同じリターンが得られる保証はありません。しかし、長期的な傾向として米国株式市場の成長が続いている以上、今後も一定の成長が期待できると考えられます。
🎯 約4,000銘柄への分散投資が生むリスク低減効果
楽天VTIの強みは、高いリターンだけではありません。圧倒的な分散効果も大きな魅力です。楽天VTIが連動するCRSP USトータル・マーケット・インデックスは、米国株式市場に上場する約4,000銘柄をカバーしています。
これがどれだけすごいことか、具体的に説明しましょう。個別株に投資する場合、その企業が不祥事や業績悪化に陥ると、株価が大きく下落するリスクがあります。例えば、かつて人気だった大企業が突然倒産したり、巨額損失を出したりした例は枝挙にいとまがありません。
しかし、楽天VTIなら1つの企業が破綻しても全体への影響は微小です。4,000銘柄に分散されているため、1社あたりの比率は平均で0.025%程度。仮にその企業の株価がゼロになっても、ファンド全体への影響はほとんどありません。
| 投資方法 | 銘柄数 | リスク水準 |
|---|---|---|
| 個別株(1~5銘柄) | 1~5 | 高 |
| S&P500連動ファンド | 約500 | 中 |
| 楽天VTI | 約4,000 | 低 |
さらに、楽天VTIは大型株だけでなく、中型株・小型株も含んでいます。S&P500が大型株500社に限定されているのに対し、楽天VTIは米国株式市場のほぼ100%をカバーしているのです。
これにより、大型株が調整局面に入ったときでも、小型株の成長が全体をサポートするという効果が期待できます。実際、景気回復の初期段階では小型株が先行して上昇する傾向があり、楽天VTIはその恩恵を受けやすい設計になっています。
💰 競合ファンドとのリターン・リスク徹底比較
それでは、楽天VTIは他の人気ファンドと比べてどうなのでしょうか?ここでは、eMAXIS Slim米国株式(S&P500)やSBI・V・全米株式といった競合ファンドとの比較を行います。
まず、リターン面を見てみましょう。直近1年間のパフォーマンスでは、eMAXIS Slim米国株式が約15%、楽天VTIが約14.97%、SBI・V・全米株式が約15%と、ほぼ同水準です。これは、いずれも米国株式市場全体の成長を反映しているためです。
3年・5年の長期リターンでも、楽天VTIは他のファンドと遜色ない、むしろ優れた成績を残しています。特に、S&P500連動ファンドと比較すると、楽天VTIは小型株の成長も取り込めるため、景気回復局面では有利になることがあります。
次に、リスク(標準偏差)を見てみましょう。楽天VTIの3年標準偏差は約14.36で、これはS&P500連動ファンドとほぼ同じ水準です。つまり、分散銘柄数が多いからといってリスクが高いわけではないのです。
コスト面では確かに楽天VTIはSBI・V・全米株式に劣りますが、それでも実際のパフォーマンスでは大きな差はついていません。これは、楽天VTIの運用が効率的に行われている証拠とも言えます。
最後に、純資産総額を見てみましょう。楽天VTIの純資産総額は1兆円を超えており、これは投資家からの信頼の厚さを示しています。純資産が大きいファンドは、繰上償還のリスクが低く、長期保有に適していると言えます。
総合的に見ると、楽天VTIは「オワコン」どころか、依然としてトップクラスのパフォーマンスを維持しています。コスト面では改善の余地がありますが、長期投資の観点では十分に魅力的な選択肢と言えるでしょう。
第3章:楽天VTI vs 競合ファンド|本当に重要な選択基準
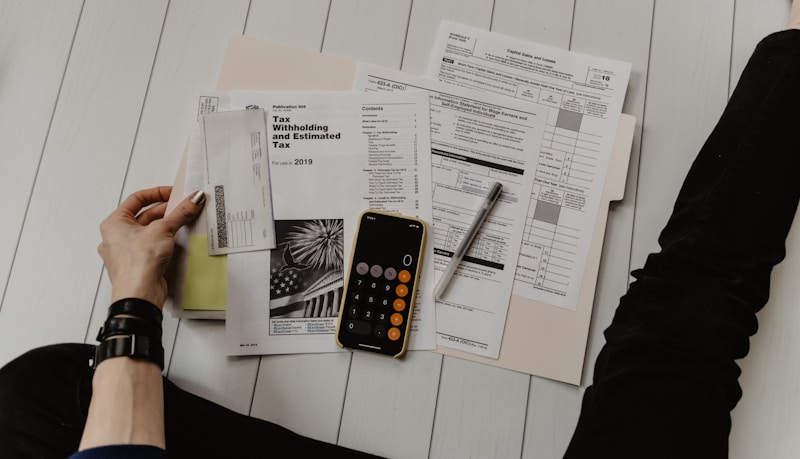
前章で楽天VTIの実力を確認しましたが、それでも「他のファンドの方がいいのでは?」と迷う方も多いでしょう。この章では、楽天VTIと競合ファンドを本質的な視点で比較し、あなたにとって最適な選択をするための基準を提示します。結論から言うと、コストだけで判断するのは危険です。
🔍 楽天VTI・SBI・V・全米株式・本家VTIの違い完全解説
全米株式に投資できるファンドは、大きく分けて3つあります。それぞれの特徴を正確に理解することが、賢明な選択の第一歩です。
①楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
楽天投信投資顧問が運用する投資信託です。最大の特徴は、100円から購入できること。クレジットカード決済でポイント還元を受けられるのも魅力です。新NISA対応で、つみたて投資枠で毎月自動積立が可能。信託報酬は0.132%(実質コスト約0.18%)とやや高めですが、利便性は抜群です。
②SBI・V・全米株式インデックス・ファンド
SBIアセットマネジメントが運用する投資信託です。最大の特徴は、業界最低水準のコスト。信託報酬0.0638%(実質コスト約0.09%)は、楽天VTIの約半分です。こちらも100円から購入でき、新NISA対応。コスト重視なら最有力候補と言えます。
③本家VTI(バンガード・トータル・ストック・マーケットETF)
米国で直接購入するETF(上場投資信託)です。経費率0.03%と圧倒的に安いですが、米ドルで購入する必要があり、為替手数料や売買手数料がかかります。最低投資額も約3万円からと高く、初心者にはハードルが高いです。
| 項目 | 楽天VTI | SBI・V・全米 | 本家VTI |
|---|---|---|---|
| 最低投資額 | 100円 | 100円 | 約3万円 |
| 購入通貨 | 日本円 | 日本円 | 米ドル |
| 実質コスト | 約0.18% | 約0.09% | 0.03%+為替手数料 |
| 新NISA対応 | ○ | ○ | △(成長投資枠のみ) |
| 自動積立 | ○ | ○ | × |
この表からわかるように、楽天VTIとSBI・V・全米株式は投資信託として似た特性を持っていますが、コストに約2倍の差があります。一方、本家VTIはコストが最安ですが、手間と初期投資額のハードルが高いのです。
では、どれを選ぶべきか?答えは、あなたの投資スタイルと優先順位によります。コスト重視ならSBI・V・全米株式、手軽さと実績重視なら楽天VTI、大口投資で最小コストを追求するなら本家VTI、という選択になります。
⚖️ 実質コスト0.07%差が30年後に与える影響試算
楽天VTIとSBI・V・全米株式のコスト差は約0.09%です。この差が長期投資でどれくらいの影響を与えるのか、具体的に計算してみましょう。
【シミュレーション条件】
・毎月3万円を30年間積立
・年率リターン5%(税引き前)
・楽天VTI:実質コスト0.18%
・SBI・V・全米株式:実質コスト0.09%
💡 30年後の資産額比較
楽天VTI(コスト0.18%)
投資元本:1,080万円
最終資産:約2,380万円
利益:約1,300万円
SBI・V・全米株式(コスト0.09%)
投資元本:1,080万円
最終資産:約2,430万円
利益:約1,350万円
差額:約50万円
このように、30年間で約50万円の差が生まれます。これは決して小さな金額ではありませんが、投資元本1,080万円に対して約4.6%の差に過ぎません。
ここで重要な視点があります。それは、「継続できるかどうか」の方が最終結果に大きく影響するということです。例えば、以下のようなケースを考えてみてください。
ケース1:コストを気にして、楽天VTIからSBI・V・全米株式に乗り換えた。しかし、乗り換え時の相場下落で一時的に損失が出て不安になり、積立を6か月中断してしまった。
ケース2:楽天VTIでそのまま継続。コストは高めだが、自動積立を30年間一度も止めなかった。
実は、ケース1のように6か月積立を中断すると、その期間の機会損失は50万円以上になる可能性があります。つまり、コスト差で得られる50万円を、継続の中断で簡単に失ってしまうのです。
また、乗り換えによる心理的ストレスや、新しいプラットフォームへの慣れなど、目に見えないコストも存在します。こうした要素を総合的に考えると、「今使っているファンドで続けやすい」ことが最優先という結論になります。
✅ 長期投資で「続けやすさ」が最大の武器になる理由
投資の成功を決める最大の要因は、「続けること」です。どんなに優れたファンドを選んでも、途中で辞めてしまえば成果は得られません。この「続けやすさ」という観点で、楽天VTIは大きな強みを持っています。
まず、100円から投資できるという点です。生活が苦しい月は金額を減らし、余裕がある月は増やす、といった柔軟な対応ができます。SBI・V・全米株式も同様ですが、楽天証券のユーザーインターフェースの使いやすさや、楽天ポイントとの連携は大きなメリットです。
次に、自動積立機能です。一度設定すれば毎月自動で買い付けが行われるため、相場を気にせず投資を続けられます。これは、感情に左右されずに投資を継続するための最強の仕組みです。
さらに、新NISA完全対応も重要です。つみたて投資枠で年間120万円まで非課税で積立でき、成長投資枠でも追加購入が可能。この制度を最大限活用できる設計になっています。
🚀 継続のための3つの秘訣
①自動積立を設定して「忘れる」
②月1回だけ残高確認(毎日見ない)
③下落時は「バーゲンセール」と考える
この3つを守れば、どんな相場でも続けられます!
実際、投資で成功している人の多くは、「何もしなかった人」です。相場の上下に一喜一憂せず、淡々と積立を続けた人が、最終的に大きな資産を築いています。
楽天VTIは、設定来8年以上の実績があり、純資産総額も1兆円を超える巨大ファンドです。この安定感と信頼性は、長期保有における心理的安心感につながります。
結論として、コスト差は確かに存在しますが、それよりも「続けやすい環境」の方が重要です。楽天VTIは、その点で非常に優れた選択肢と言えます。もちろん、SBI証券をメインで使っている人はSBI・V・全米株式を選ぶのも合理的です。大切なのは、自分にとって続けやすいプラットフォームで投資することなのです。
第4章:新NISAと楽天VTIで賢く資産形成する戦略

2024年から始まった新NISA制度は、投資家にとって史上最強の優遇制度と言われています。楽天VTIとこの制度を組み合わせることで、税金をほとんど払わずに資産を増やせる可能性があります。この章では、新NISAの仕組みを理解し、楽天VTIを使った実践的な資産形成戦略を具体的に解説します。
🎁 つみたて投資枠120万円を最大活用する方法
新NISA制度には2つの投資枠があります。1つ目はつみたて投資枠で、年間120万円まで積立投資ができます。2つ目は成長投資枠で、年間240万円まで投資できます。楽天VTIはどちらの枠でも購入できますが、まずは「つみたて投資枠」を最優先で使うのが賢い戦略です。
なぜつみたて投資枠を優先すべきなのでしょうか?理由は3つあります。第一に、自動積立が設定できること。一度設定すれば毎月自動で買い付けが行われるため、相場を気にせず継続できます。第二に、ドルコスト平均法の効果が得られること。定額積立なら、価格が高いときは少なく、安いときは多く買えるため、平均取得単価を下げられます。第三に、心理的負担が小さいこと。一括投資は「いつ買うか」のタイミングに悩みますが、積立なら悩む必要がありません。
具体的な活用方法を見てみましょう。年間120万円の枠を使い切るには、毎月10万円の積立が必要です。しかし、いきなり10万円は難しいという人も多いでしょう。その場合は、自分のペースで始めて、徐々に増やすのがおすすめです。
💡 段階的積立プラン例
1年目:毎月3万円(年間36万円)
2年目:毎月5万円(年間60万円)
3年目:毎月7万円(年間84万円)
4年目以降:毎月10万円(年間120万円)
無理なく増やすことで、継続しやすくなります!
また、ボーナス月に増額設定をするのも効果的です。例えば、通常は毎月5万円、ボーナス月(6月・12月)だけ15万円にすれば、年間90万円の積立が可能です。この柔軟性が、つみたて投資枠の大きな魅力です。
さらに重要なのは、非課税期間が無期限という点です。従来のNISAは非課税期間が5年や20年と決まっていましたが、新NISAは一度投資すれば永久に非課税です。つまり、20年後に2,000万円になっても、40年後に5,000万円になっても、売却時の利益に税金がかかりません。
通常、投資で得た利益には約20%の税金がかかります。例えば、100万円の利益が出た場合、約20万円が税金で引かれてしまいます。しかし、新NISAならこの20万円が丸々手元に残るのです。これが新NISA最大の魅力といえます。
📅 ドルコスト平均法で価格変動を味方にする仕組み
つみたて投資枠を使う最大のメリットは、ドルコスト平均法が自動的に機能することです。この仕組みを理解すると、相場の上下が怖くなくなります。むしろ、下落を「チャンス」と捉えられるようになります。
ドルコスト平均法とは、定額で定期的に買い続ける投資方法です。価格が高いときは少ない口数しか買えませんが、価格が安いときはたくさんの口数を買えます。この結果、平均取得単価が自然に下がるという効果があります。
具体例で見てみましょう。毎月3万円ずつ楽天VTIを買うとします。1か月目の基準価額が30,000円なら1口買えます。2か月目に基準価額が20,000円に下落したら1.5口買えます。3か月目に25,000円に回復したら1.2口買えます。
| 月 | 基準価額 | 購入口数 |
|---|---|---|
| 1か月目 | 30,000円 | 1.0口 |
| 2か月目(下落) | 20,000円 | 1.5口 |
| 3か月目(回復) | 25,000円 | 1.2口 |
| 合計 | 投資額9万円 | 3.7口 |
この例では、3か月で合計3.7口を購入しました。平均取得単価は約24,324円(9万円÷3.7口)です。もし1か月目に9万円を一括投資していたら、3口しか買えず、その後の下落で損失を抱えていました。しかし、積立投資なら下落局面で多く買えるため、回復時の利益が大きくなるのです。
この仕組みを理解すると、市場が下落したときに「やった!安く買える」と思えるようになります。実際、投資で成功している人ほど、下落を喜ぶ傾向があります。なぜなら、将来の成長を信じているからです。
ドルコスト平均法のもう1つの利点は、感情を排除できることです。「今は高いから買わない方がいい」「もっと下がるまで待とう」といった迷いがなくなります。機械的に毎月買い続けることで、タイミングを読む必要がなくなるのです。
実際のデータを見ると、過去20年間で「最悪のタイミング」で一括投資した人よりも、「毎月コツコツ積立」を続けた人の方が、最終的なリターンが高かったというケースが多数報告されています。これが、積立投資の力なのです。
🚀 2026年以降の米国株式市場成長シナリオと投資戦略
新NISAで楽天VTIに投資する場合、長期的な市場見通しも重要です。2026年以降の米国株式市場はどうなるのでしょうか?最新の専門家予測と、それに基づく投資戦略を見ていきましょう。
大手証券会社の予測によると、2026年の米国株式市場は年率約9%の上昇が見込まれています。これは過去30年の平均的な成長率と同水準で、極端な楽観でも悲観でもない、現実的な予測です。その背景には、①企業業績の拡大傾向、②FRB(米連邦準備制度理事会)の金融緩和政策、③AI・テクノロジーセクターの継続的成長があります。
🎯 20年積立の未来シミュレーション
条件:毎月5万円を20年間積立(年率7%想定)
・投資元本:1,200万円
・運用資産:約2,600万円
・利益:約1,400万円
新NISA活用で、この1,400万円が全額非課税!
通常なら約280万円の税金が引かれるところ、ゼロで済みます。
もちろん、市場には調整局面もあります。過去のデータを見ると、10年に1度程度の割合で大きな下落が起こっています。リーマンショック(2008年)、コロナショック(2020年)などです。しかし、重要なのは「下落は一時的」で、「長期的には回復・成長する」という歴史的事実です。
実際、過去100年以上のデータを見ると、米国株式市場はあらゆる危機を乗り越えて成長してきました。世界大恐慌、2つの世界大戦、オイルショック、ITバブル崩壊、リーマンショック、コロナショック…すべてを経験しながらも、長期的には右肩上がりを続けています。
では、どのような投資戦略を取るべきでしょうか?答えは「淡々と積立を続ける」ことです。相場が上がっても下がっても、自動積立を止めない。これが最も確実な戦略です。
さらに、余力がある人は成長投資枠も活用しましょう。つみたて投資枠で毎月10万円を積み立てながら、ボーナス時などに成長投資枠で追加購入するのも効果的です。生涯投資枠は1,800万円なので、この枠を埋めることを長期目標にすると良いでしょう。
最後に、リバランスについても触れておきます。楽天VTI100%で運用するのも良いですが、年齢やリスク許容度に応じて、債券や現金を組み合わせるのも賢明です。例えば、20代なら楽天VTI100%、40代なら80%、60代なら60%といった具合に、徐々に安全資産の比率を増やすと安心です。
結論として、新NISAと楽天VTIの組み合わせは、長期資産形成の最強の武器です。つみたて投資枠で毎月コツコツ、ドルコスト平均法で価格変動を味方につけ、米国株式市場の長期成長を取り込む。この戦略を20年、30年続けることで、大きな資産を築ける可能性が高まります。
第5章:迷ったときの判断フレーム|継続・乗り換えチェックリスト

ここまで楽天VTIの実力や活用法を見てきましたが、それでも「本当にこのまま続けていいのか?」「他のファンドに乗り換えるべきか?」と迷う瞬間があるかもしれません。この章では、迷ったときに冷静に判断できるフレームワークを提供します。感情ではなく、明確な基準で判断することが成功への鍵です。
🤔 「今すぐ乗り換え」が正解とは限らない3つの理由
SNSやブログで「SBI・V・全米株式の方がコストが安い」「楽天VTIから乗り換えた」という情報を見ると、焦る気持ちになるかもしれません。しかし、今すぐ乗り換えることが必ずしも正解ではないのです。その理由を3つ説明します。
理由①:乗り換えコストが発生する
既に楽天VTIを保有している場合、それを売却して別のファンドを買うと、売却時に利益が出ていれば税金がかかります。新NISA枠で保有していれば非課税ですが、旧NISAや特定口座で持っている場合は約20%の税金が引かれます。100万円の利益なら20万円の税金です。この税金コストを考えると、コスト差で得られるメリットが相殺されてしまう可能性があります。
理由②:乗り換え期間の機会損失
売却して新しいファンドを買うまでの間、現金で保有することになります。この数日~数週間の間に市場が上昇すると、その上昇分を逃してしまいます。例えば、乗り換え期間中に10%市場が上昇したら、100万円なら10万円の機会損失です。これもコスト削減のメリットを上回る可能性があります。
理由③:心理的ストレスと継続性の低下
乗り換えを実行すると、新しいプラットフォームに慣れる必要があります。また、「本当に正しい判断だったか」という不安も生まれます。こうしたストレスが、投資を続ける意欲を削ぐことがあります。投資で最も重要なのは「継続すること」ですから、心理的負担が増えるのは避けたいところです。
💡 乗り換えよりも「新規積立」を変更する
既に保有している楽天VTIはそのまま置いておき、新規の積立だけSBI・V・全米株式に変更する方法もあります。これなら、売却コストも機会損失もゼロ。心理的負担も小さく、「良いとこ取り」ができます。
つまり、「乗り換え」は必ずしもベストな選択ではないのです。特に、既に数年間積立を続けていて、含み益が出ている場合は、そのまま継続する方が合理的なケースが多いです。
📋 6つの判断軸で自分に最適な選択を見極める
それでは、継続するか乗り換えるかを判断するために、6つの判断軸を用意しました。これらの質問に答えることで、自分に最適な選択が見えてきます。
| 判断軸 | 継続を推奨 | 乗り換えを検討 |
|---|---|---|
| ①投資期間 | 20年以上の長期 | 10年未満の中短期 |
| ②現在の含み損益 | 大きな含み益あり | 含み損または小幅利益 |
| ③使用プラットフォーム | 楽天証券メイン | SBI証券メイン |
| ④コスト重視度 | 継続性を重視 | 1円でも安く |
| ⑤心理的負担 | 変化がストレス | 変化を楽しめる |
| ⑥資産規模 | 300万円以下 | 1,000万円以上 |
この表を見ながら、自分がどちらに当てはまるか考えてみましょう。「継続を推奨」が4つ以上なら、今のまま楽天VTIを続けるのが賢明です。「乗り換えを検討」が4つ以上なら、新規積立を変更するか、計画的に乗り換えを進めるのもありでしょう。
特に重要なのは、①投資期間と②現在の含み損益です。20年以上の長期投資を考えているなら、0.09%のコスト差は誤差の範囲です。また、既に大きな含み益がある場合、売却して税金を払うのはもったいないです。
逆に、SBI証券をメインで使っていて、まだ楽天VTIを始めたばかり(含み益が小さい)なら、乗り換えのデメリットが小さいので、変更を検討する価値があります。
🔄 分割移行で失敗しないポートフォリオ再構築手順
それでも「やっぱり乗り換えたい」と判断した場合、いきなり全額を動かすのは危険です。失敗しないための分割移行プランを紹介します。
【分割移行の基本ルール】
①全体を4~6回に分けて移行する
②3~6か月かけてゆっくり進める
③市場が大きく下落したタイミングでは移行を一時停止する
④新規積立は即座に変更してOK
🔄 6か月分割移行プランの例
現在:楽天VTI 300万円保有
1か月目:新規積立をSBI・V・全米株式に変更
2か月目:楽天VTI 50万円売却→SBI購入
3か月目:楽天VTI 50万円売却→SBI購入
4か月目:楽天VTI 50万円売却→SBI購入
5か月目:楽天VTI 50万円売却→SBI購入
6か月目:楽天VTI 50万円売却→SBI購入
7か月目:残り50万円を状況見て判断
このように分割することで、極端なタイミングリスクを避けられます。もし移行期間中に市場が大きく変動しても、一部は既に移行済み、一部はまだ保有中なので、影響を平準化できます。
また、移行中に「やっぱり楽天VTIのままで良かった」と思った場合、いつでも中止できるのもメリットです。柔軟性を持たせることが、後悔しない判断につながります。
最後に、記録を残すことも大切です。移行の理由、タイミング、金額を記録しておくと、後で振り返ったときに学びになります。「あのとき、なぜこの判断をしたのか」を明確にしておくことで、次の判断もスムーズになります。
結論として、迷ったら「継続」が基本です。乗り換えを検討する場合も、慌てず、計画的に、分割して進めましょう。投資は長期戦です。焦らず、自分のペースで、着実に資産を築いていくことが何より大切なのです。
まとめ:楽天VTIはオワコンではない|自分軸で投資判断を

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。楽天VTIが「オワコン」という評価は、短期的な視点や一面的な情報に基づいた誤解であることがおわかりいただけたと思います。実際の数字を見れば、楽天VTIは依然としてトップクラスのパフォーマンスを維持しており、長期投資に十分値する選択肢です。
重要なのは、「他人の評価」ではなく「自分の目的」です。あなたが投資をする理由は何でしょうか?老後の安心、子どもの教育資金、経済的自由…目的はそれぞれ違います。そして、その目的に向かって継続できる仕組みを選ぶことが、成功への最短ルートです。
楽天VTIは、100円から始められ、自動積立ができ、新NISAにも完全対応している優れたファンドです。コストは確かにSBI・V・全米株式より高めですが、その差は継続することの価値に比べれば小さなものです。
投資は不安がつきものです。相場が下がれば「失敗したかも」と思うし、SNSで「他の商品の方がいい」と見れば迷います。でも、長期で積立を続けた人ほど成果を得られるのは歴史が証明しています。
最後に問いかけます。あなたの未来のために、今日からできる小さな一歩は何でしょうか?毎月3万円の積立を始める、自動積立の設定をする、新NISAの口座を開設する…どんな小さなことでも構いません。行動を始めた人だけが、未来を変えられます。
楽天VTIは「オワコン」ではありません。あなたの資産形成を支える、力強いパートナーです。自分を信じて、一歩を踏み出してみませんか?

コメント